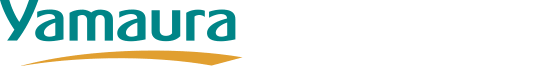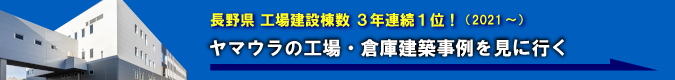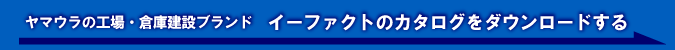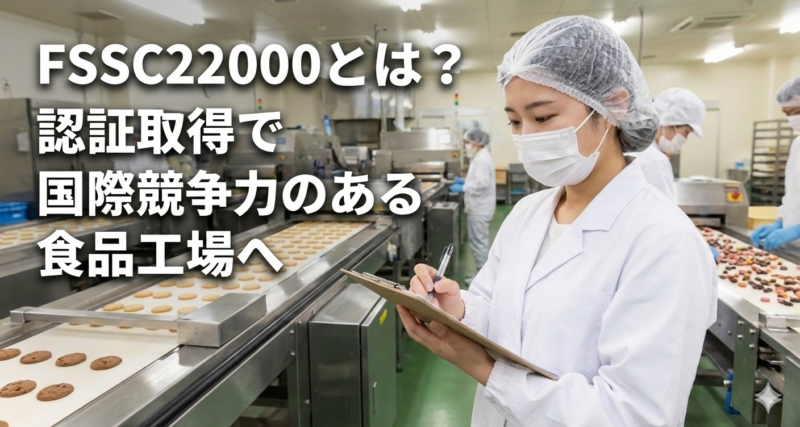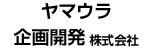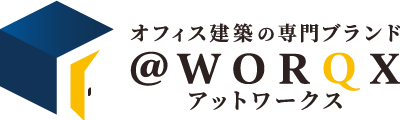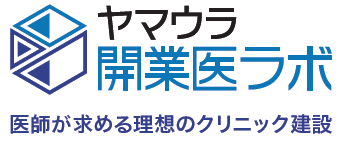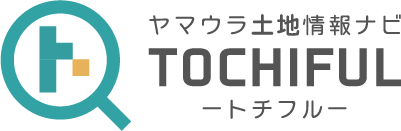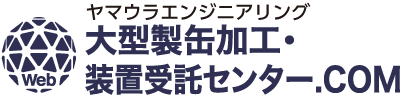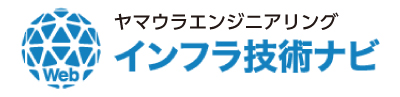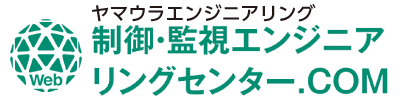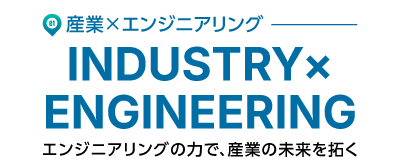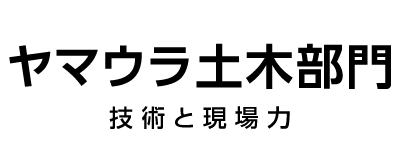建設コラムColumn
工場を建てるのは、一大プロジェクトです。目的を明確にするところから、依頼先の選定・設計・施工・検査・稼働まで、ひとつひとつの判断が将来の工場運営に大きな影響を及ぼします。何から始めればいいのか、どこに注意すべきなのかと、初めての工場建設に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、工場設計の基本的な手順と、失敗しないために押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてみてください。
目次
工場設計の手順【6ステップ】
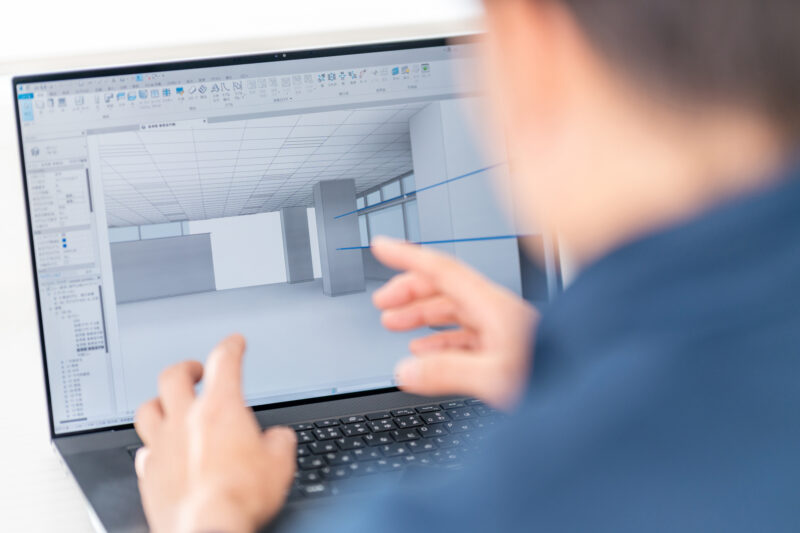
まずは工場設計の手順を6ステップにわけて説明します。
- 目的・規模を決める
- 信頼できる会社を選ぶ
- 基本設計を考える
- 詳細な図面を描く
- 建設工事を行う
- 建物検査をクリアする
1.目的・規模を決める
まずは建設の目的と規模を明確にしましょう。ここが曖昧だと、途中で設計変更が必要になり、コスト増や工期遅延の原因になりかねません。
「生産量をどれだけ増やしたいのか」「従業員は何人規模になるのか」といった基本条件を決めずに進めると、設備やレイアウトに不備が生じ、後から追加工事が必要になる可能性も。何を生産するためにどんな規模感の工場を建てるか、あらかじめ大枠を考えておきましょう。
2.信頼できる会社を選ぶ
信頼できる会社を選ぶことも大事です。工場建設は都市計画法や建築基準法、工場立地法など、多くの法令に適合させる必要があります。また、建設地の都道府県や市区町村で条例がそれぞれあり、この確認も必須です。
実績が豊富で法令対応やメンテナンス体制が整っている事業者を選べば、トラブルも最小限に抑えられると期待できます。
法規制に不慣れであったり地域性の理解が低い会社に依頼すると建物計画が進まず、場合によっては重大なコンプライアンス違反の原因となったり、設計のやり直しや工事中断につながるかもしれません。見積もりが安いから、という安易な理由で依頼先を選ばないようにしましょう。
3.基本設計を考える
基本設計は、生産性や作業効率を大きく左右する大事なポイントです。例えば、生産施設内の従業員の移動距離が長すぎるとそれだけで作業時間が増え、生産効率に影響します。現在の作業動線を分析し、より使い勝手に配慮したレイアウトを考えると失敗しにくくなります。
工場が円滑に稼働するために必要な基盤となるインフラをどこに配備するかも、この段階で検討しましょう。具体的には、電気・ガス・水道・空調・換気・ネットワーク環境・セキュリティ・監視設備・発電設備について考える必要があります。これらの機器の入れ替えや増設は、いつか起こりうるものです。それを想定した設備容量やレイアウトを、この段階で検討しておくと、将来変更が生じても柔軟に対応できます。
また、この段階で金額調整までしておきましょう。実施設計に取りかかると大きな変更はできなくなるため、基本設計の段階で予算に合っているか必ず見ておいてください。
4.詳細な図面を描く
基本設計ができたら、建物の詳細図面を描いていく実施設計に入ります。配線・配管・機械配置などを設計士がより詳細に詰めていきます。特に、後から変更が難しい電気容量や給排水設備などインフラはこの段階で設計士が作成した図面をしっかり確認しましょう。設計時に運用を想定し、必要な容量や配置を正確に決めることで、竣工後、安定稼働しやすくなります。
5.建設工事を行う
図面ができて工事見積を確認し、工事契約を締結したら、いよいよ建設工事に入ります。施工が進む中で、設計者は監理者として図面通りに施工されているかの確認や仕上げ材の選定、あるいは必要に応じて設計変更を行います。施工管理者に任せきりにせず、発注者側も進捗状況を把握しておきましょう。
大規模工事ではわずかな工程遅れが操業開始時期の遅延につながり、損失が大きくなってしまいます。スケジュールが押したりトラブルが発生した際にすぐ対応できるよう、施工管理者と定期的に情報共有を行うようにしておきましょう。
6.建物検査をクリアする
建設工事が完了しても、建築完了検査、消防検査に合格しなければ工場を使用できません。建築完了検査では、建築基準法に関する建物の細やかな規定に関して、消防検査では消防法に係る消火・防災設備に関して現地検査と書類検査が実施されます。
検査で法基準を満たしていないと、是正工事が必要になり、完成が後ろ倒しになってしまう可能性も。施工期間も法令基準を意識し、必要に応じて事前確認を行うことで、検査をクリアしやすくなります。
工場設計で後悔しないためのポイント

工場を建ててから設計変更が必要になったり、予想以上にコストがかさんだりすることは避けたいものです。そこで、ここでは設計段階で気をつけるべきことを5つお伝えします。
- 近隣住民に配慮する
- メンテナンス・ランニングコストを考慮する
- 関連する法律を確認する
- 妥協できない部分の優先順位を決める
- 専門知識が豊富な会社を選ぶ
近隣住民に配慮する
工場を建てるなら、近隣住民への配慮が必要です。騒音・振動・異臭などが原因でトラブルになると工場の稼働開始が遅れたり、最悪の場合は事業継続に支障が出ます。
長期的に安定して事業を続けるには、地域との信頼関係を築くことが大切です。設計段階から室外機や排気口の位置を工夫して迷惑をかけないよう気をつけたり、建設前に説明会を開催し、近隣住民が不安を感じないように配慮したりしましょう。
メンテナンス・ランニングコストを考慮する
建設費用だけでなく、稼働後のランニングコストやメンテナンスも考える必要があります。初期費用を抑えるために設備のグレードを下げると、後々の電力消費や部品交換頻度が増え、結果的に運用コストが膨らむことも。設計段階で耐久性や保守性を考慮し、長期的なコストを見積もりましょう。
近年ではSDGsの一環として、太陽光発電や蓄電池などの再生可能エネルギーの導入を検討する企業も増えています。初期投資が大きくなりますが、長期的には電力コストの削減につながる可能性が高く、環境対策の面からも積極的に取り入れるべきです。
関連する法律を確認する
工場を建てる際には、工場立地法・都市計画法・建築基準法など多くの法律を遵守する必要があります。適合しない場合は、建築確認済証が発行されず工事着手ができません。基本的には設計事務所に任せるところですが、発注者自身も基本的な法令の概要を把握し、どのような規制が適用されるのか理解しておくことが大切です。
妥協できない部分の優先順位を決める
予算や仕様のバランスを取るために、優先順位を明確にする必要も出てきます。例えば、品質保持のための温度管理や防塵性能など生産に直結する部分は妥協せず、それ以外の仕様は必要に応じて調整する、など基本方針を定めましょう。最初にコンセプトと優先順位を決めておけば、見積もり調整や設計変更の際にも迷わず判断でき、無駄なコストを抑えつつ必要な性能を確保できます。
専門知識が豊富な会社を選ぶ
「工場」といっても、食品工場と金属加工工場では必要な設備や管理基準が大きく異なります。
業種に応じた設計ノウハウがある会社なら、必要な基準を満たしつつ効率的なレイアウトを提案できるでしょう。工場設計を任せる前に、建てようとしている工場の専門知識と実績が豊富にあるか確認しておくことが大切です。
まとめ

今回は工場の設計手順から、後悔しないために知っておくべきポイントまでを解説しました。
工場建設は多くの工程が関わるため、早い段階から全体像を整理し、長期的な視点で準備を進めることが大切です。地域ごとの法令や周辺環境への配慮も必要になるため、地元事情に詳しい会社に相談することで、よりスムーズに進められるでしょう。
長野県・山梨県の工場設計はヤマウラへ
山梨・長野エリアでの工場建設をご検討中の方は、地域に根ざした実績を重ねてきた当社へ、ぜひお気軽にご相談ください。
まずはカタログを見たいという方は下記よりダウンロード下さい。