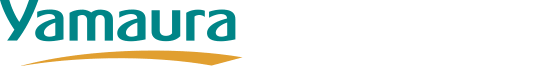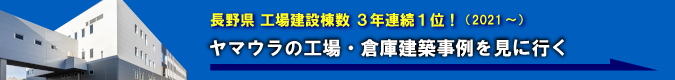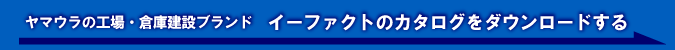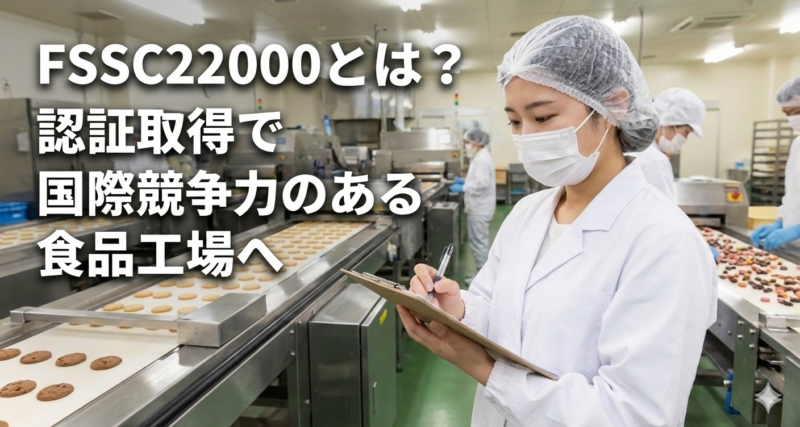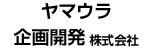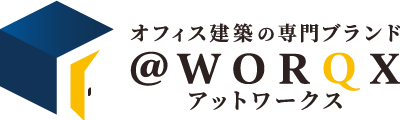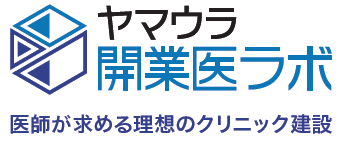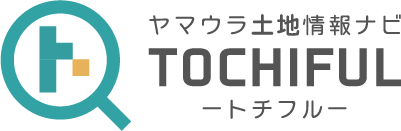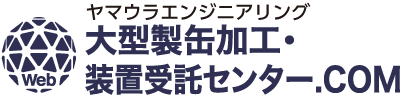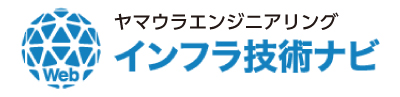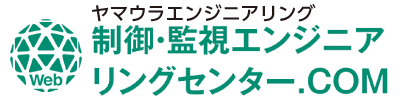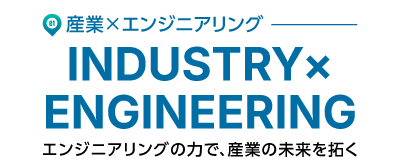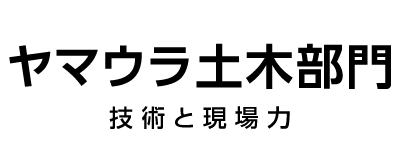建設コラムColumn
「市街化調整区域では工場が建てられない」などと聞いたことがある方も多いかと思います。しかし、市街化調整区域内でも規制がありますが建てられる方法・条件があります。本記事では、市街化調整区域で工場を建設する方法を解説いたします。
目次
市街化調整区域の基本的な理解
都市計画法にて「市街化調整区域」に区分されていますが、どういった目的で定められているかなど、まずは概要を解説します。
市街化調整区域とは?
都市計画法において、都道府県は「市街化区域」と「市街化調整区域」及び「非線引き区域」に区分する事ができます(区域区分制度)。※
市街化区域は、都市の無秩序な市街化を防止し計画的に市街地整備を進めるために、都市計画区域を優先的に市街化する目的に対し、市街化調整区域では「当面できる限り市街化を抑制すべき」として定められます。
※区域区分は、基本的には任意で定めるものです。ただし、三大都市圏の一部や政令指定都市など、一定の区域では必ず定めなければなりません。
.jpg)
国土交通省 「市街化区域と市街化調整区域〔区域区分〕」 より引用
長野県の場合
4都市計画区域(4市1町計5市町 R4年3月31日現在)において区域区分が定められています。
|
区分 |
長野都市圏 |
松本都市圏 |
||
|
都市計画区域名 |
長野 |
須坂 |
松本 |
塩尻 |
|
市町村 |
長野市 |
須坂市、小布施町 |
松本市 |
塩尻市 |
詳しくは、計画地の市町村へご確認下さい。
ちなみに・・・
旧豊科町では市街化調整区域が定められていましたが、合併後の安曇野市は、旧豊科町を含む旧都市計画区域を統合し、市街化調整区域の線引きが廃止されました。これにより、旧豊科町は「非線引き区域」となり、開発に対する規制が緩和されました。
市街化調整区域の特徴
市街化調整区域の主な特徴をご案内します。以下の特徴を理解しておきましょう。
- 開発※や建設の制限が厳しい
許可取得後の用途変更や建築条件・規模等制限があります。
- 比較的土地の価格が安い
前述のように開発・建設の制限が厳しく、全体的に需要が低いことから価格が安い傾向にあります。
- 立地・環境について
市街地から距離があり、自然に囲まれ静かな環境であることが多い。
インフラ整備が不十分なケースが多い。(電気・ガス・上下水道、道路など)
※開発(行為)とは、主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、
(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいう。
(参考:国土交通省 都市計画ページ)
市街化調整区域で工場を建設するポイント

市街化調整区域では原則として開発行為、建築行為は認められません。しかし、市街化を促進するおそれがないものものとして、最低限必要と認められるものについては、特例的に建築が認められる場合があります。市街化調整区域について、建設できる条件(開発用途)を解説します。
市街化調整区域で認められる主な開発用途(都市計画法第34条)
市街化調整区域では、都市計画法第34条に基づく立地基準に適合する場合に限り、開発行可されます。工場建設に関連する主な許可要件は以下の通りです。
- 鉱物資源・観光資源の有効利用施設(第2号)
セメント製造業、粘土かわら製造業に供する施設等
当該市街化調整区域内にある鉱物資源の有効利用のための施設
観光資源の有効利用上必要な宿泊施設若しくは休憩施設又は観光資源の鑑賞のための展望台等施設
- 農林水産物の処理・加工施設(第4号)
当該市街化調整区域で産出される農産物、林産物、水産物の処理、加工に必要な施設
農産物の集出荷場等
- 既存工場の関連施設(第7号)
既存工場に関連する工場を建設する施設で以下の条件を満たす施設
① 既存工場との関連性(密接関連工場)
・既存工場に対して、自己の生産物の5割以上を原料又は部品として納入しており、
かつそれらが既存工場における生産物の原料又は部品の5割以上を占める場合。
・生産活動(生産、組立、出荷等)及び輸送等に関して効率化が図られるものであること。
・予定建築物の高さは、原則として10m以下のものであること。 他、条件あり
② 工場を拡張する場合の条件
・現に適法に使用されている工場施設において、施設内容の同一性を維持しつつ敷地拡張を行おうとする場合に適用する。
・現在の敷地が狭隘であるため敷地を拡張せざるを得ないと認められること。
・既存の工場施設の敷地に隣接し、かつ既存の敷地と一体的に利用されること。
・拡張する敷地は従前の敷地と同面積以下であること。 他、条件あり
(参考:茨城県 法第34条第7号許可基準)
市街化調整区域での工場建設のステップ

実際に市街化調整区域で工場を建設するためには、どのようなステップで進めていくのか、申請についてご案内します。
開発許可申請のプロセス
建物を建設するには、まず開発許可申請を行う必要があります。開発行為をスムーズに進める事が工場の建設が成功するポイントになります。開発行為に掛かるプロセスは以下になります。
① 開発計画についての事前相談(各地域を所管する建設事務所の建築課)
計画の概要を示した図面等、必要な書類を持参の上、所管する建設事務所で事前相談を受ける必要があります。
② 公共施設管理者との同意・協議(都市計画法第32条)
申請前に開発行為に関係ある公共施設の管理者等に協議し、同意が必要です。
(公共施設:道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路等)
③ 関係権利者の同意(都市計画法第33条)
開発行為に関する工事の施行の妨げとなる権利を有する者の同意が必要です。
(妨げとなる権利:土地の所有権、永小作権、地上権、賃借権、質権、抵当権、先取特権等)
④ 開発許可申請(都市計画法第29条)
申請先は原則、都道府県知事になります。ただし、政令指定都市や中核市などのように市長が許可権者となる場合があります。長野県の場合は、長野市と松本市は各市へ申請し、その他の市町村は長野県(各建設事務所経由)へ申請します。
⑤ 開発許可取得
許可申請に基づき審査が行われたのち、許可証が交付されます。
⑥ 工事着工
工事中は「開発許可済の標識」を開発区域の見やすい場所に掲示する必要があります。
⑦ 完了検査
工事完了(自主検査を含む)し、完了届を提出します。完了届を基に県が検査を行います。
⑧ 完了公告
完了検査後、検査済証が交付され、完了公告となります。
↓
建築物工事着工
上記のステップで進めていく必要がありますが、特に最初に行う事前相談が重要です。計画について、開発行為の許可申請等の要否や手続き方法を事前に相談することで計画の流れなどが見えてきます。まずは、市町村へ確認しましょう。
(参考:長野県 開発許可等の申請の手引き)
市街化調整区域での工場建設のご相談はヤマウラへ
これまで述べてきたように市街化調整区域で工場を建設するには多くの制限があります。まずは設計会社や建設会社に相談してみると良いでしょう。
株式会社ヤマウラでは、土地や法律に詳しいスタッフが多く在籍しております。ぜひ、ヤマウラにご相談下さい。
土地の提案から設計、施工まで一括で請負うことができます。まずはカタログ請求からでも結構です。以下をご確認下さい。