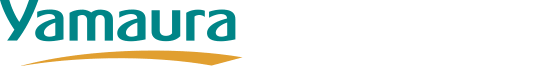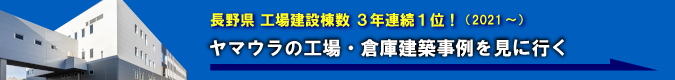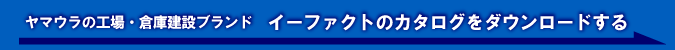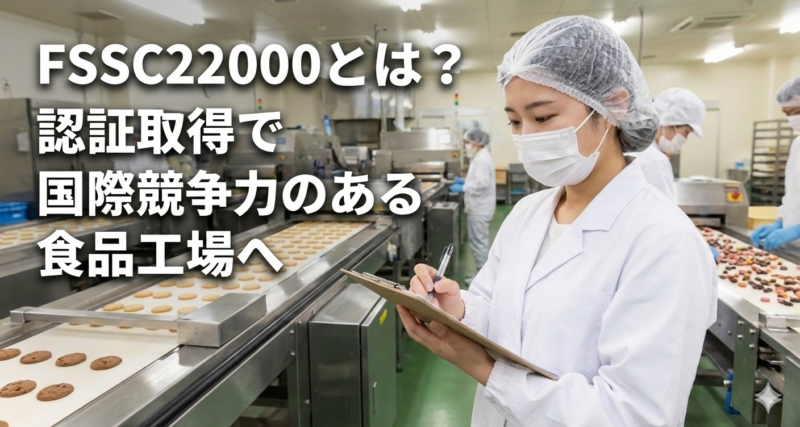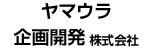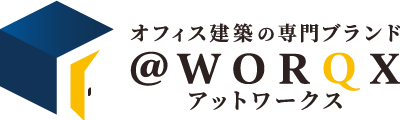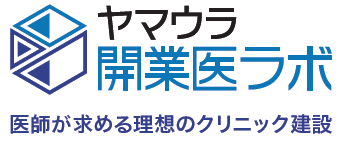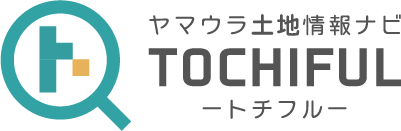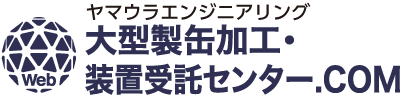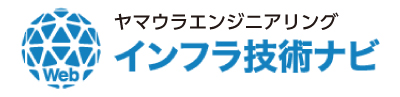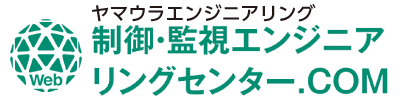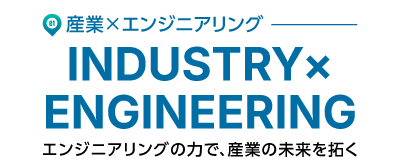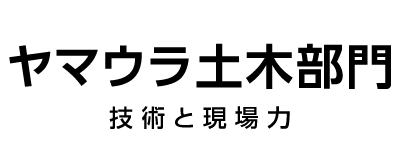建設コラムColumn
製造業にとって投資の要ともいえる工場建設。成功のためには、適切な準備と計画的なアプローチが不可欠です。
本記事では、経営者やプロジェクト担当の皆様が効率的なアプローチで進められるよう、工場完成までの全プロセスを俯瞰できる情報をお届けします。
目次
工場建設の準備プロセス
工場建設はなんといっても大きなプロジェクト。何から手を付けなければならないか迷ったり、あれもこれもと急いてしまうかもしれませんが、まずは整理して一つ一つ手をつけていきましょう。
工場建設の目的と対象市場の明確化
工場建設を始める前に、まず建設の目的を明確に定めておきましょう。この建てる工場の規模、設備、立地などの基準をどこに置くか、全ての決定の基盤となります。
以下のような要素から、生産能力増強、効率化、新製品対応などの目標を、具体的な数値として定めていきます。
・対象となる市場と成長性
・生産する製品の種類と生産量
・競合他社の動向と差別化戦略
・将来的な事業拡張の可能性
適切な立地選定と土地取得の手続き
工場の立地は事業の成功を左右する大きな要素です。新たな土地を求める場合、検討にあたって基準になるのは、以下のようなポイントです。
・交通アクセス(高速道路、港湾、空港)
・労働力の確保(人口動態、技能水準)
・原材料の調達コスト
・顧客との距離
・用地取得コスト
・用途地域等の法的確認
災害の多い昨今、BCP(事業継続計画)の観点を盛り込み、あえて現在と離した生産拠点を検討に含めるのも現実的に有効な戦略といえます。保有する土地がある場合でも、工場建設という滅多にない機会に、生産拠点の立地について改めて見直してみてもよいでしょう。
なお、法的要件に関しては、例えば基本的には建てられない農地や市街化調整区域でも、必要な手続きを踏むことで建設が許可されるケースもあります。複雑な条件が絡みますので、土地を探すならできるだけその地域の事情と建設関連法制に詳しい専門家に相談してみるのもよい手段です。
(参考:調整区域での工場建設法を解説!・工場を建設できる土地の条件・法律)
設計会社または設計・施工会社選定
工場建設の成功で必須の要素といえば、主要なパートナーとなる設計会社の選定でしょう。
設計を設計のみの事務所に任せるか、設計施工一貫の会社に任せるかは、最初の大きな選択肢です。
弊社では設計と施工の整合性や工期の短縮、総合的なコストの面から設計・施工一貫の形をお勧めしていますが(詳しくはこちら:工場建設の設計・施工)、設計事務所に依頼する場合、この段階では設計事務所のみを決定し、後から入札を実施するなどして施工会社を決めることになります。
いずれにしても、まっさらな状態から会社選びを行うなら、選定の基準としてまずは過去の実績・経験から確認していくとよいでしょう。単に数だけでなく、過去のその会社の同業種における経験や、手掛けている物件の規模などを確認して決定してください。見積、提案を複数社から検討する際は、イニシャルコストに目がいきがちですが、課題解決の提案力があるか・ランニングコストはどうか等、経営戦略として長期的に判断することが重要です。なお、設計施工一貫の場合は特に、大きな規模の取引になります。会社の財務状況の健全性のチェック等も忘れずに実施しましょう。
予算策定と資金調達の準備
工場建設には多額の投資が必要です。予算の大枠の確認や資金調達の計画を早めに行うことで、スムーズに工程を進めることができます。どのような資金がどのぐらい使えそうか、初期段階であたりを付けておきましょう。
主な資金調達の方法としては以下のようなものがあります。
・自己資金
・銀行融資
・補助金・助成金の活用
・リース・割賦の活用
工場の内容によっては、クラウドファンディングで資金を募集するケースも見られるようになりました。商品が一般顧客向けのもので新規性がある場合など、マーケティングも兼ねて検討してみてもよいでしょう。
基本計画から実施設計まで

準備作業に一通りの目途がついたところで、いよいよ計画・設計に進みます。
基本計画でインプットを決定
設計に入る前に、工場建設の骨格を決めるのが基本計画です。ここでよいものができれば、建設プロジェクトの成功にぐっと近づける重要な工程です。
まず、準備プロセスで定めた目的・目標について、改めて明確化しましょう。ゴールを定めることで、今後の設計・施工工程すべての指標になってきます。また、本格的な設計工程に入る前のこの段階は、発注会社としてはぜひ社内体制を固めておきたい時期です。しっかりと検討し、プロジェクト推進のためのメンバーや役割分担を整えてください。
また、既存工場の敷地内に新築する場合は、電力や給排水などインフラ設備の配置や容量の確認が重要です。継続する既存工場の製造部門との協議も行い、新工場完成までの流れをこの段階で整理することが必要です。基本計画時の成果物として、計画概要書や要求仕様書、工程表等を完成させます。また、専門家を交えた検討を基に、概算見積を作成してこの段階のコストも把握するのも重要なフェイズです。
基本設計時の内容と注意ポイント
基本計画で事業全体像を捉えたのちに、設計は基本設計と実施設計の2段階で進めます。
基本設計から、工程を平面図や立面図にまとめる、いわゆる設計の工程に入っていきます。基本計画で定めた要求事項等に基づき、建物の具体的な形やデザインが見えてきます。
工場にとって重要な工場全体の配置・ゾーニング計画も、生産ラインの配置や人・物の流れをシミュレートした動線等もここで定めていきます。必要に応じてシミュレーションソフトなどを用い、検証を行うとよいでしょう。
当然のことながら、この後の実施設計、資材の調達、工事開始と後の工程に行くほど手戻りが難しくなります。以下のような点に注意しながら検討漏れがないように進めていきます。
・説明や情報提供が必要な各関係者の合意形成
・起こりうる変更への柔軟性や冗長性
・省エネルギー、防災安全性、近隣住民対策等、多角的な視点での検討
実施設計で行うこと
実施設計では、基本設計で決定した内容を、実際の工事で使用する構造図や設備図等の施工図面に落とし込めるレベルまで具体化していきます。正確な建設工事の金額は、この工程を経なければ算定できませんが、金額を算出した結果、どうしても予算と合わないこともあり得ます。場合によっては基本計画に戻っての調整が必要になってきます。
設計・施工分離で行う場合、実施設計でできた書類をベースとして各業者に見積を依頼し、入札を行って施工業者を決定するといった作業も必要となります。
実施設計の終盤には、決定を基に書類を整備し、建築確認申請をはじめとする各種申請が待っています。
ここを通過できないと、建築には入れません。業者と協力してスムーズな対応を進めていきましょう。
「積算」という工程
発注側からはあまり見えませんが、どの材料をどのぐらい使うか、何の業者で何時間作業が必要なのか、図面等を基に計算を行う「積算」という工程の存在を知っておいてください。
実は建物というものは、種類が多く複雑な材料や作業の見積に加え、計画中の価格の変動等もあって、金額を算出すること自体がかなり大変なのです。
ただ、発注者の立場からすると、実施設計が終わるまでどのぐらいの金額がかかるか全くわからない状態では、計画も立てられないでしょう。そこで、計画初期段階ではわかる範囲の仕様で、過去の実績等から概算を出すなどしています。
工場建設中の注意点

工事期間は基本的には設計・施工会社に任せることになりますが、定期的な進捗確認や発生する相談事項への対応等を行う必要があります。コミュニケーション体制づくりが鍵となりそうです。
工事準備
設計完了後はすぐにでも工事に入りたいところですが、多くの材料やたくさんの種類の作業が必要な工場建設では、モノや人が適切な時期に現場に入ってこられるよう、様々な調整を行わなければなりません。先立って資材の発注・調達等を行う準備期間が必要となります。
この期間は事前に施工業者が決まっている設計・施工一貫方式であれば、実施設計の間を使ってある程度短縮することも可能です。
工事中の定期的な進捗確認
工事期間中は基本的には設計・施工会社の作業となりますが、工事の進捗に合わせて相談事項が発生しますので、施工会社と定期的にコミュニケーションをとっていく体制が必要です。週次・月次での会議の開催や、報告書の確認等で、工事の進捗を把握しておきましょう。
規模が大きく、期間も長期となる工場建設では様々なトラブルが発生する可能性があります。
例えば、悪天候による工事遅延や、資材調達の遅れ、設計変更による追加工事や地下埋設物の発見などが比較的よくあるケース。
想定外の出来事を100%防ぐのは難しいことですので、トラブルが起こったら早期に相談してもらい、ともに解決していく姿勢を持つことで、影響を最小限にとどめる施策が可能になるでしょう。
完成検査と最終確認手続き
工事が完了すると、建築確認の完了検査が行われ、官庁等の機関により申請通り安全な建物ができているか等が確認されます。この他、建物の用途により、消防やガス設備検査等、様々な検査が実施されます。行政等による法的検査が完了したのち、施主検査を経て建物の引き受けとなります。通常、この時点で工事費残金の決済をすることになります。
検査をクリアし工場を使用する準備が整ったら、設備や機器の試験運転を実施します。部分的な動作確認から、段階を踏んで全体的な試験運転を行い、最終調整を行います。
気づかなかった問題が浮かび上がる可能性もありますから、充分な期間をとって進めていきましょう。また、建物引き受けの前後で建物登記の手続きを行います。建物表示登記は土地家屋調査士に建物調査を依頼し、権利保全の建物保存登記は司法書士に依頼することとなります。
工場建設成功のためのプラスα
製造を営む企業として大きな転換点となる工場建設という機会を利用して、検討してみていただきたいヒントをご紹介します。
コンセプトのある工場づくり
建物の建設はブランディング戦略の観点でも重要です。単なる生産拠点ではなく、経営者の方々の想いを形にし、企業価値の向上につながるような明確なコンセプトの設定もぜひ検討してみてください。
よく見られるのは工場見学で、自社のファンづくりを促すような仕掛けです。例えば自然との調和を感じさせるデザイン、自動化したラインや最新のロボット、活き活きと働く従業員の姿など、自社の理念をアピールできるような見学ルートを設定できたら大成功ですね。
工場内ショップや、広い庭の開放などという形で、地域に溶け込んでいる企業もあります。もちろん、顧客開放を伴わなくても、しっかりとしたコンセプトはWEBサイトやパンフレット等で扱うだけでもパワーのあるコンテンツとなるでしょう。他工場の成功事例も参考にして、厚みのある計画づくりをしてみませんか。
省エネ・創エネとBCP
省エネルギー・創エネルギー対策についても、工場建設時にぜひ検討したいテーマの一つです。高騰する電気代等のランニングコストは抑えることにつながることはもちろん、災害時の事業継続計画(BCP)としても大きなメリットがあります。
自然を利用した創エネルギーだけをとっても、代表的な太陽光発電だけでなく、風力発電やバイオマス、小水力発電など、様々なシステムが考えられます。工場の特性や立地を利用してメリットのあるものを採用することで、前段のコンセプトにもつなげることができるでしょう。
まとめ
工場建設は製造業の将来を決定づける重要な投資です。本記事でご紹介した工場建設の流れを参考に、一つ一つの工程をしっかりと計画的にクリアしていきましょう。会社の一大プロジェクトの大成功の一助になることを祈っています。
長野県・山梨県の工場の建設はヤマウラへ
建設したい工場の業種にあった用地選定や使える補助金の確認など、工場建設に必要な知識は幅広く、どこに相談すればいいのか迷われる担当の方も多いのでは。
長野県・山梨県で建築をお考えなら、まとめてヤマウラにお任せください。長野県内での工場建設棟数の実績が3年連続でナンバーワンの当社が、オールインワンの体制で貴社の工場建設をバックアップ致します。