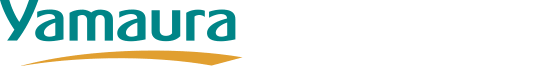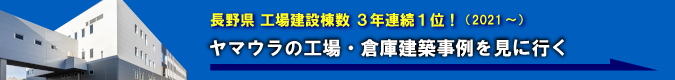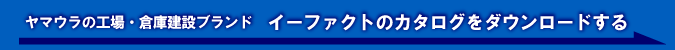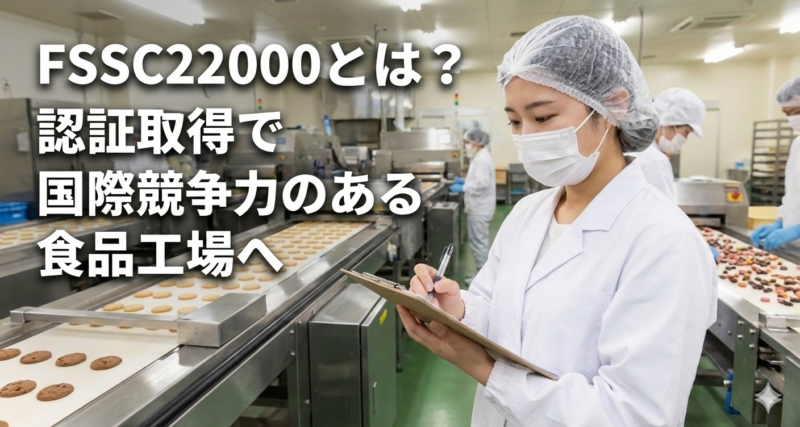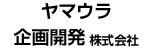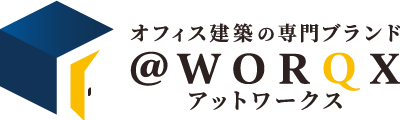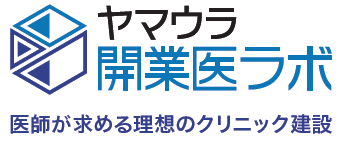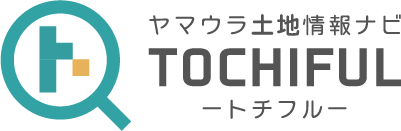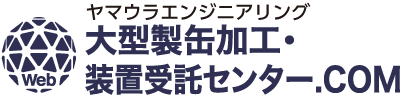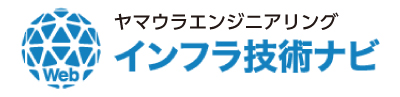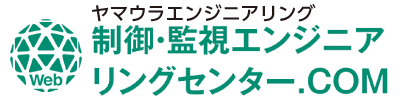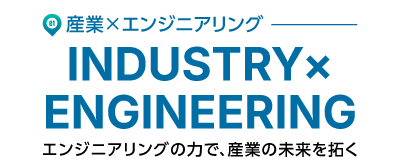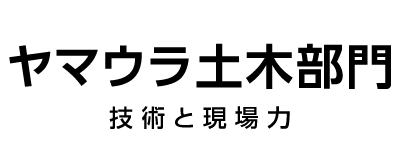建設コラムColumn
工場や倉庫、事務所などの施設を運営していると、「既存不適格」という言葉を耳にすることがあるでしょう。特に増築や改修を検討する際に初めて自社施設が既存不適格建築物であることを知り、想定外のコストや工期延長に直面するケースが少なくありません。
本コラムでは、施設管理する上で知っておきたい既存不適格の基本概要から、違法建築との違い、そして具体的な対応方法まで解説いたします。
目次
既存不適格(建築物)とは何か

既存不適格建築物とは、建築当初は建築基準法などの法令に適合していたものの、その後の法改正や都市計画の変更により、現行の法規制に適合しなくなった建築物を指します。
このように、建築時に適法であった建物は「違法」というわけではなく、法改正後も原則としてそのまま使用し続けることができます。ただし、増築や大規模な改修を行う場合には、現行基準への適合が求められるケースが多く、企業にとって大きな課題となります。
違法建築との決定的な違い
ここで明確に理解しておきたい点は、既存不適格と違法建築の違いについてです。この違いを混同すると、適切なリスク管理ができません。
既存不適格建築物と違法建築物の比較
| 既存不適格建築物 | 違法建築物 | |
| 建築当時 | 建築当時は法令に適合していた | 建築当初から法令に違反していた |
| 要因 | 法改正や都市計画変更により不適合状態になった | 建築確認を受けずに建築した、または確認内容と異なる建築を行った |
| 是正命令 | 是正命令を受けることはない | 是正命令や使用停止命令を受ける可能性がある |
| 罰則 | そのまま使用し続けることが可能 | 放置すると罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象となる |
| 検査済証 | 交付されている | 交付されていない、または内容と異なる |
違法建築の場合は即座に是正措置が必要ですが、既存不適格の場合は計画的な対応が可能です。
万が一、違法建築をされている可能性が高い場合は、直ちに設計・建設会社等専門家にご相談下さい。
既存不適格となる主な原因・チェックするポイント
把握しておくべき、既存不適格となる主な原因・チェックするポイントを整理します。
耐震基準の改正
1981年6月1日の建築基準法改正により、耐震基準が大きく変更されました。これ以前に建築された建物は、いわゆる「旧耐震基準」で設計されており、現行の「新耐震基準」を満たしていないケースが多く見られます。製造業の工場や物流倉庫では、この問題が特に顕著です。
その他、建築基準法・都市計画法の改正
建築後、法律や条例、都市計画が変更されて、以前は適合していた建物が現在の基準を満たさなくなることがあります。例えば、用途地域・防火地域の変更や建ぺい率、高さ制限などの改正といった様々な原因で既存不適合建築物になってしまうことがあります。
どういった時に是正対応が必要か
「既存不適格建築物」は建築基準法第3条第2項に規定されており、これまで述べてきたように既存不適格建築物となった場合でも、すぐに是正しなければならないわけではありません。それでは、どういった時に是正対応が必要なのかご説明します。
①増改築、大規模修繕・大規模模様替え等の実施
原則として、建築物全体を現行の規定に適合させることが求められます。
②一定の用途変更を実施
法令で求められた規定について、現行の規定に適合させることが求められます。
※100㎡以下の部分を特殊建築物に用途変更する(建築確認不要)場合にも同様に適合義務あり。
なお、①の増築においては「一体増改築」と「分離増改築」によって適合方法が異なります。
「一体増改築」は、既存建物と増築部分を構造的に一体化させる増築方法でこの場合においては、増改築部分と既存部分が一体で現行の構造計算基準に適合させる必要があります。
一方で「分離増改築」は、既存建物と構造上切離し、独立した建物を増築する方法であり、エキスパンションジョイントで2つの建物を繋げる増築になります。この場合は、増改築部分は現行の構造計算基準に適合させる必要がありますが、既存部分は耐震診断基準に適合されていれば、問題ありません。建築基準法86条の7は「既存の建築物に対する制限の緩和」に定められています。

引用:国土交通省「既存不適格建築物について」より
増値改築部分が延べ床面積の1/20かつ50㎡以下の場合は、増改築部分は現行の構造計算基準に適合しなければなりせんが、既存部分は危険性が増大しなければ特に適合は求められません。
増改築等に係る建築確認申請の実務

既存不適格建築物を増築や改修する際の流れや用意するものなど実務について解説します。
確認申請のフロー
まずは計画について設計・建設会社に相談してみましょう。
法に関わる難しい検討が必要の為、下記のフローを設計・建設会社と一緒に進めると良いでしょう。
①対象建築物の確認
・計画建物の用途、構造、規模などを整理し適応対象になりうるか、
あたりをつけておく
②既存建物の資料確認・調査
・既存建物を建設した当時の建築確認済証、検査済証ほか図面など建築時期や構造が分かる資料があるか確認
・耐震診断など現況調査が必要
③計画建物の設計(検討)
・②の資料との照査
・プランニング、構造検討
④確認申請
既存不適格調書等の必要書類を添付し確認申請を行います。
申請時の必要書類(既存不適格調書)
既存不適格建築物の増築等に係る建築確認の申請を行う際、「既存不適格調書」を添付する必要があります。調書の作成についてのガイドラインも策定されていますので、参考にしてみてください。
参考:国土交通省「既存建築物の活用の促進について」
長野県の「既存不適格調書」県様式はこちら
主な提出書類は以下になります。
〇既存不適格調書
・現況の調査書
・既存建築物の平面図及び配置図
・新築又は増築等の時期を示す書類
・基準時以前の建築基準関係規定への適合を示す図書等
まとめ

旧耐震基準の建物など築年数が経っている建物は、既存不適合建築に該当する場合があります。増改築等計画の有無関らず、事前に今ある建物が既存不適合建築物に該当しているか把握しておくことも重要です。今後、増改築を検討されている場合は、まず専門家に相談してみましょう。
長野県・山梨県で増改築のご相談はヤマウラへ
ヤマウラでは新築はもちろん、既存建物の増築・改築・大規模修繕の対応も承ります。経験豊富なスタッフがご対応いたします。まずは、既存の建物が「既存不適格建築物」に該当しそうなのかなどご気軽に相談いただけたら幸いです。
なお、「既存不適格建築物」は建築基準法第3条第2項に規定されており、認められている建物になります。