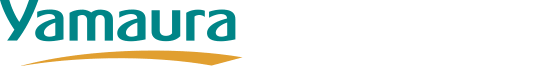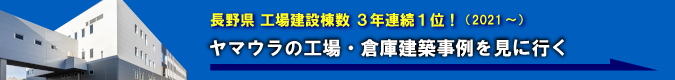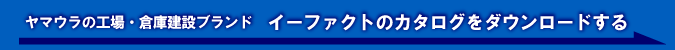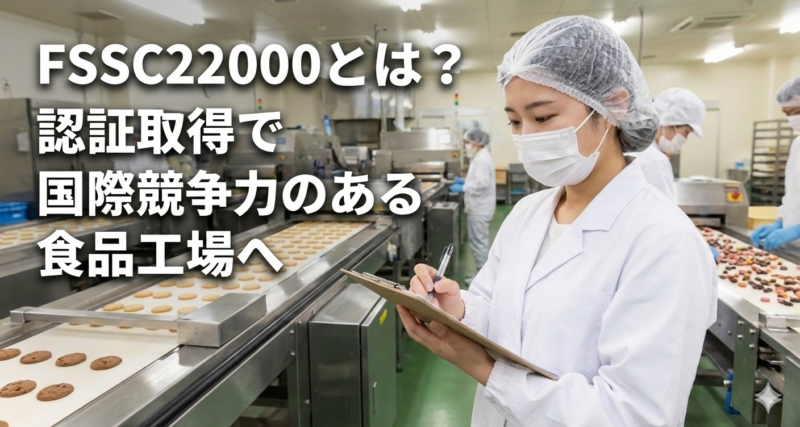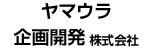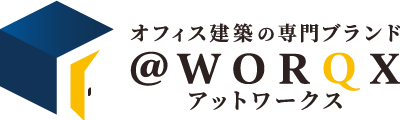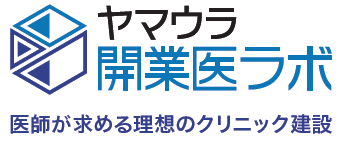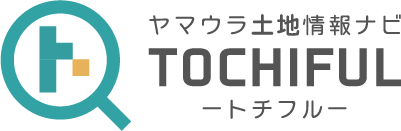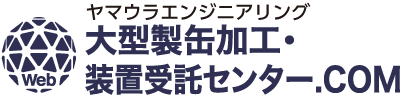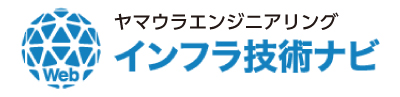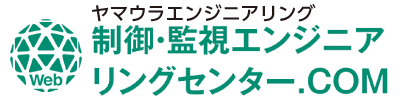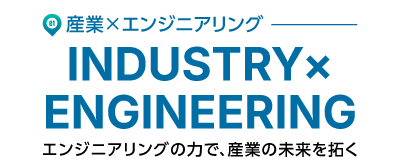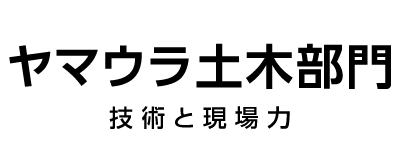建設コラムColumn
倉庫建設を検討している事業者にとって、まず気にかかる建設費用。適切な資金計画を立てるためには、建設にかかる費用の全体像を把握することが重要です。本記事では、倉庫建設の費用相場から資金調達方法、コストダウンのポイントまで、実際の事業計画に役立つ情報を詳しく解説いたします。
目次
倉庫建設費用の概要
倉庫建設の総費用は、建築工事費に加えて設備費や諸経費があり、新設の場合は土地の取得に関わる費用も必要となります。事業計画を立てる際は、これら全体のコストを考慮した資金計画が必要です。
倉庫建設の坪単価の目安
まず、建物のそのものの金額の目安を把握しておきましょう。
2024年政府統計では、倉庫建築の全国平均坪単価は約60.7万円となっています。(eStat 建築物着工統計 2024年より)
こちらは小さな倉庫から大きな倉庫まで、仕様も様々な倉庫の平均単価ですので参考にしにくいかもしれません。同じ統計の各構造の棟数と坪単価についても以下に紹介しておきます。
倉庫用途の建築申請棟数 2024年度 (eStat 建築物着工統計より)
| 構造 | 棟数 | 坪単価 |
| 木造 | 1,888 | 51.8万円 |
| 鉄骨造 | 10,233 | 59.2万円 |
| 鉄筋コンクリート造 | 189 | 68.0万円 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 20 | 117.2万円 |
| その他 | 409 | 33.1万円 |
ここでは併せて、近年激しい建設費の変動についても確認しておきましょう。
同じ建築物着工統計で、3年前、2021年には、倉庫の全国平均坪単価は約43.1万円でした。たった3年で1.4倍にもなっており、近年の上昇が激しいことが確認できます。
建設費については、今後も人件費の高騰などでさらなる上昇が見込まれています。
費用をなるべく安く抑えるために「早めに建てる」といった決断も必要な場面といえるかもしれません。
設備関連の費用
設備に関しては、どんな建物でも必要な電気・空調・給排水設備等に加え、当然ながら用途に応じて大きく費用が変動します。
ものを置くだけのごく簡単な倉庫から、防火設備が必要な危険物倉庫、業務として荷物を預かる営業倉庫、食品や薬品等の保管する低温倉庫、重量物を容易に移動できる天井クレーン付き倉庫など様々な倉庫があり、法律で必要な設備が規定されているものもあります。
目標とする機能が実現できるよう、漏れがないようしっかりと設計・設備業者との打合せを進めましょう。
土地に関わる費用
土地費用は建設費と並び投資額を大きく左右する要素となります。
地価はイニシャルコストとなることはもちろん、その後の税金などの点でランニングコストにも影響を与えこともチェックしておいてください。
その土地だからかかる費用もあります。造成費や地盤改良費、運が悪いと工事が始まってから埋蔵物の処理費がかかる可能性も。これらはかなり高額になる可能性があるものですので、土地選びの段階から注意して進めましょう。
また、土地の区画形質の変更を伴う一定面積以上の造成は開発行為の許可申請が必要で、該当する計画はその費用も計上しましょう。
その他、土地に関連しては登記費用や不動産取得税、印紙税等の手続き費用も見込んでおく必要があります。
倉庫の構造と費用相場の関係

倉庫も建設方法により、初期投資額、耐用年数、維持コストが大きく異なります。以下に、最適な選択のヒントとしてそれぞれの特徴を取り上げます。
テント倉庫
ビジネス用途で、コストのかからない選択肢が必要な際、検討されるのがテント倉庫です。
坪単価は使用するタイプによってかなり幅がありますが、通常数万円~二十数万円ぐらいで済みます。
移設や撤去が容易ですので一時的な資材置き場などに向いています。ただし耐久年数は10~15年程度に限られるため、それを超える年数使用が見込まれる場合は注意して選択してください。
名前からわかる通り、断熱性や防犯性能はあまり期待できません。猛暑の近年、中で働く人にとっては過酷な環境となることが多いため、導入される際は熱中症対策なども考えておくとよいでしょう。
木造倉庫
木造は比較的安価で、小規模の倉庫に適しています。
2024年の平均坪単価は、51.8万円でした。
比較的安価で、素材として断熱性・調湿性に優れる点などがメリットです。
ただし構造的に制約を受けるため、大きな空間をとることには限界があります。大きいもの・重いものを想定する場合は選択が難しくなります。
鉄骨造
2024年の着工統計でも、倉庫としてダントツで採用されており、用途に向いた建築と考えられているのが鉄骨造です。2024年の平均坪単価は、59.2万円でした。
鉄骨造には、軽量鉄骨造と重量鉄骨造があり、慣例的に軽量鉄骨造を規格化したものを「プレハブ建築」、重量鉄骨造を規格化したものを「システム建築」と呼んでいます。
コストが安いのは細い鉄骨を使うプレハブ建築です。工期が短い点などもメリットとなります。
ただし、使うのは通常6mm未満の細い鉄骨ですから、大きな空間を作る用途にはあまり向いていません。耐久性や断熱性を持たせるのも難しくなります。
大きな空間を必要とするなら、お勧めなのはしっかりと太い柱を使った「システム建築」です。
断熱性能等の確保も比較的しやすく、耐久性も高いため、ものの保管に適した建物を作りやすい建築といえるでしょう。
鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート
鉄骨造より更にコストが高くなるのが鉄筋コンクリート造(RC)と鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)です。
2024年の平均坪単価は、鉄筋コンクリート造で68.0万円、鉄骨鉄筋コンクリート造で117.2万円でした。
鉄筋コンクリート造、更に頑丈な構造の鉄骨鉄筋コンクリート造は、きっと皆さまのイメージ通り、非常に耐久性が高く断熱性能などの点でも優れた構造です。
耐久性はもちろん、断熱性や防音性能、防災性能やセキュリティといった長所がありますが、鉄骨造と比べ大空間がとりにくいという短所もあり、倉庫としては特別な理由があるときの選択肢といえます。
資金調達手段の比較

倉庫建設の資金調達は、事業の安定性と将来の収益性を左右する重要な要素です。各手段の特徴を理解し、最適な組み合わせを選択しましょう。
自己資金
自己資金は金利負担がなく、使途に制限を設けられないというメリットがあるため、ある程度は用意したいものです。
ただし、全額自己資金での建設などを目指す必要はありません。手元資金の減少によるリスクや、節税効果の点でのデメリットもあります。
事業用の建物での投資としては、自己資金は2・3割程が理想的と言われますので参考にしてください。
融資
・日本政策金融公庫
国が株式の100%を保有する政策金融機関です。製造業や小売業、サービス業などの中小企業を対象に4,800万円(特定設備資金は7,200万円)を限度に融資が受けられます。金利が低く、実績が少ない企業でも審査に通る可能性があります。
面談があるなど、融資を受けるまでの手続きは比較的手がかかります。
・自治体による融資
県や市町村による制度で、名称や対象、限度額等はそれぞれ異なります。融資までの時間はかかりますが、やはり金利は抑えられて安心です
建てようとする自治体のWEBサイト等で確認してください。
・民間金融機関(銀行、信用金庫等)
もっとも一般的となるのが民間の融資です。
銀行であれば審査はそれなりに厳しいですが、限度額がなく、金利は比較的低く抑えられるでしょう。
信用金庫は利用が中小企業に限定されていたり、可能な地域が決まっていたりとある程度要件がありますので注意してください。
社債、出資など
企業ならではの資金調達方法として、出資や社債という方法もあります。手間はかかりますが、会社にとって重要な投資では選択肢に入れておきたいものです。
・社債
有価証券として投資家から資金を借り入れるのが社債です。新会社法が制定され、株式会社以外の会社も発行が可能となりました。経営への干渉を受けることなく資金を調達するメリットがありますが、利息や手数料等のコストがかかる点がデメリットです。一般投資家を幅広く公募する公募債や、少数の投資家に直接引き受けてもらう私募債等があります。
・出資
通常は出資者に対して、株式を提供する形をとり、株式数に応じた議決権(経営権)を譲渡します。
費用を抑えるためのポイント
合理的に投資費用を削減する方法として、以下のような手段が考えられます。
補助金・助成金をしっかり活用
国や県などによる補助金や助成金の活用ができれば、実質的な建設費負担を大幅に軽減できる可能性があります。例えば、「中小企業成長加速化補助金」「中小企業新事業進出促進補助金」など今後も募集がありそうな補助金はぜひチェックしておきましょう。
新規事業用の投資にしか使うことができないもの、設備には使えるが建物には使えないもの、省エネルギー対策設備のみに使えるもの等、様々な補助金・助成金があります。事業計画の見通しを説明する書類作成など、申請に手間のかかるものも多く、確実なスケジュール管理が求められます。
設計・施工業者としっかり協力、相談のうえで進めてください。なお、融資先(金融機関等)や補助金のコンサル会社に相談しても良いでしょう。
土地探し・用地取得
倉庫用地は一般の住宅や店舗等と必要とする広さやニーズの点で大きな違いがあります。
特に面積が広い事業用地の取り扱いは通常、不動産会社でもそれほど多くはないもの。お買い得の土地探しをしたいなら、すでに出ている情報だけを頼りに探しても難しいかもしれません。
不動産会社だけでなく建築会社も含め、地元の事業用地の取り扱いノウハウがある会社に条件を提示し、時間をかけて探す形を検討してもよいでしょう。
建築方法によるコストダウン
先に確認したとおり、構造によってかかる金額は変わりますが、安い構造に変えて必要な目的を満たせなければ本末転倒です。品質を下げず金額を下げられる可能性があるのは以下のような方法です。
・設計施工一貫
設計は別に依頼し、入札を開催して複数の施工会社に見積をとる形でコストダウンを図ることもありますが、かかる手間暇と時間の負担が生じます。業者選び次第にはなりますが、1社で調整できて当初から施工方法を検討できる設計施工一貫の方が安く済むことが多いでしょう。
・規格化された建築方法を選ぶ
シンプルな形状で問題ない倉庫でしたら、ぜひ規格化された建築を採用しましょう。
例えば重量鉄骨造なら規格化された「システム建築」を選べば、標準化された部材と効率的な施工により、在来工法比で2割程度のコスト削減が可能です。
・施工地域の業者を選ぶ
設計会社も施工会社も、施工地域にはできるだけ近い業者の方が交通費や宿泊費を削減でき、安くできる可能性があります。
・他の工事との合併発注
もし他の施設も建設を行うなどの予定があれば、同じ時期に行うことにより業者の移動コストなどを削減できます。
大型の倉庫建設のご相談はヤマウラへ
ヤマウラなら、土地探しから補助金申請、設計・施工まで、ワンストップで専門的なご相談をいただけます。ランニングコストも含めて皆さまの事業にとってよい倉庫になるよう、長期的な視点でコストパフォーマンスの良いご提案に努めます。
長野県・山梨県で倉庫建設をお考えなら、ぜひ貴社の安心の倉庫建設のパートナーとして、東証プレミアム上場・100年続く実績をもつ当社をご検討ください。