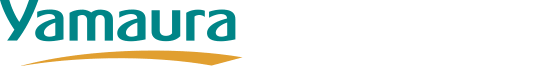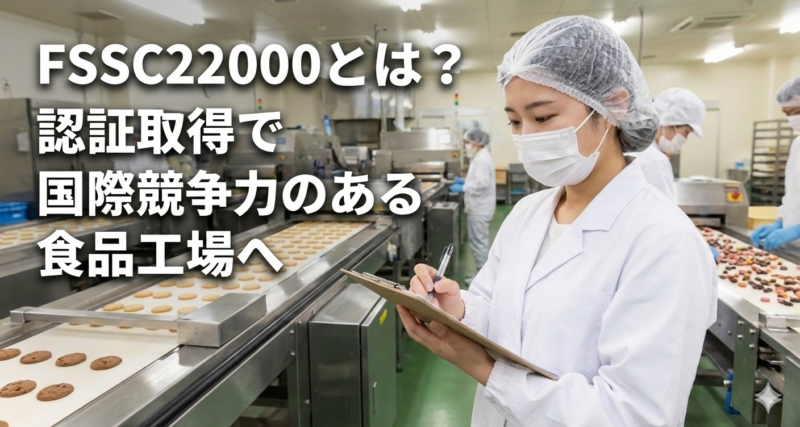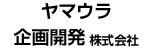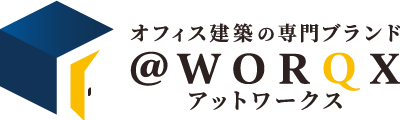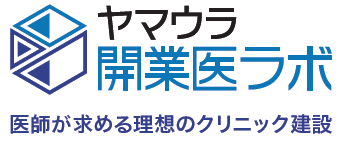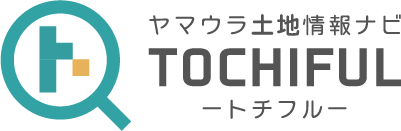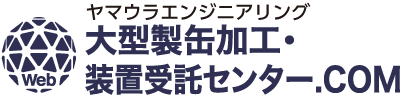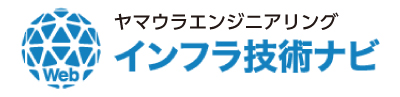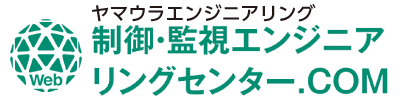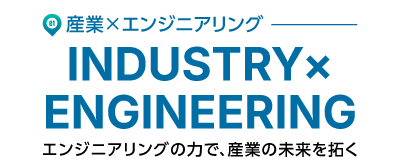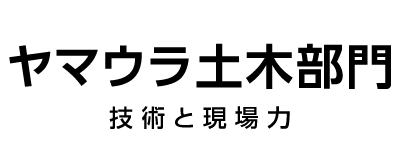建設コラムColumn
食品工場の建設が初めての場合、どの用途地域に建てられるか、どのように土地を選び、どのような法規制が関係するかわからず、計画の第一歩でつまずく方も少なくありません。
この記事では、立地選定に必要な建築基準法や工場立地法などの法令知識、周辺環境との関係性、土地探しの際に押さえておきたい視点をわかりやすく解説しています。初めての工場建設に向けた前提知識として、ぜひ参考にしてみてください。
目次
食品工場と用途地域の関係
「用途地域」とは、都市計画法に基づいて定められた土地利用のルールです。都市計画法は、市街地の健全な発展や住環境の保護を目的に、建築可能な建物の種類や用途を地域ごとに制限しています。食品工場は原則として「工業系用途地域」で建築可能ですが、「住居系用途地域」では建設が制限されるケースが多く、事前の確認が不可欠です。
また、用途地域が指定されていない区域には、市街化調整区域や非線引き都市計画区域、特例白地区などがあり、建築自体は可能でもインフラ整備が不十分な場合があるため、慎重な検討が求められます。
さらに、食品工場を建設する際は、工場立地法や食品衛生法、自治体独自の条例など、確認すべき法令は多岐にわたります。用途地域の特性を正しく理解し、法令面と環境面の両方から立地条件を精査することが、食品工場の適切な計画につながります。
食品工場を建てられる用途地域

ここでは、食品工場が建設できる用途地域について地域ごとの解説をします。
工業専用地域
「工業専用地域」は、食品工場を含む各種工場の建設にもっとも適した用途地域です。住宅が建てられない分、工場の建設に関しては制限が少なく自由度が高いため、大規模な設備導入や将来的な拡張にも柔軟に対応できます。周辺環境も工業利用を前提としているため、工場立地に非常に有利な条件が整っており、食品工場を建設するのに有利な環境です。
工業地域
「工業地域」は、食品工場の立地としてもっとも現実的な候補地となります。工業専用地域と同様に多様な工場建設が可能で、自由度が高いのが特徴です。住宅や店舗の建築も一部認められていますが、工場立地に不利となる制限は少なく、周辺環境との調和を図りながら計画を進めやすい地域といえます。
準工業地域
「準工業地域」は、工場だけでなく一定の住居や商業施設とも共存できる用途地域です。大規模な重工業には必ずしも向きませんが、周辺環境との調和を図りながら小規模な食品工場や加工場を設置するには適した地域といえます。
生活利便施設や住宅が併存できるため、従業員の通勤や地域との共生にも有利であり、「工業地域」と同じく、現実的な立地候補として検討しやすい用途地域です。
第一種住居地域・第二種住居地域
「第一種住居地域」および「第二種住居地域」は、主に住宅の良好な環境を守ることを目的とした用途地域であり、基本的に食品工場の建設は認められていません。ただし例外的に、食品工場以外の用途で延べ床面積150㎡以内といった小規模な加工所や作業所であれば建設可能な場合があります。
大規模な食品工場には不向きですが、地域住民の生活に支障を与えない範囲で小規模な製造や加工を行う施設であれば立地できる余地があります。
食品工場立地で考慮すべき条件

ここでは、食品工場の建設計画を立てる際に確認しておくべき条件について解説します。
建築基準法との関係
食品工場の立地を考えるときは、建築基準法のルールも大切です。「建ぺい率」や「容積率」は、敷地にどのくらいの規模や高さの建物を建てられるかを決める要素になるため、工場計画に直結します。また、接している道路の幅によっては、建築許可や搬入出のしやすさに影響が出る可能性もあります。
さらに、防火地域や準防火地域に指定されている場合は、建物の構造や使える材料に制限がかかるため注意が必要です。こうした条件をあらかじめ確認しておくことで、安心して計画を進められ、後のトラブルを防ぐことにつながります。
インフラ環境
食品工場の立地を考える際には、インフラ条件の確認も欠かせません。上水・下水・電気・ガスといったユーティリティーが安定して供給されるかは、生産の継続性に直結します。特に、食品工場では水を大量に使用するため、水質や水圧の安定性が重要です。
また、排水についても、水質汚濁防止法に準じた処理施設の整備が求められています。万が一、基準を満たしていなければ操業に支障をきたす可能性もあるため、注意が必要です。これらを事前に確認することで、安心して計画を進められるでしょう。
物流アクセス
食品工場の立地を考える際には、物流アクセスの良し悪しも大きなポイントです。たとえば、高速道路や主要幹線道路へのアクセスが良ければ、原材料の搬入や製品の出荷がスムーズに行え、輸送コストの削減にもつながります。
特に、食品工場は加工品の鮮度が重要です。配送時間の短縮は、品質保持に直結するため、交通網の利便性は欠かせません。また、渋滞や交通規制の影響を受けにくい立地を選ぶことで、安定した供給体制を確保でき、取引先や消費者からの信頼にもつながります。
周辺環境・住民との関係
食品工場の立地では、周辺環境や住民との関係に十分な配慮が欠かせません。製造過程で発生する臭気や騒音は生活環境に影響を与えるため、防臭設備や防音対策を計画段階から検討することが重要です。
また、騒音規制法や振動規制法といった関連法令の基準を確認し、適切な対応を行う必要があります。特に住居地域に近接する場合は、操業時間や搬入出の方法にも注意を払い、地域住民とのトラブルを未然に防ぐ姿勢が求められます。
食品工場建設におけるヤマウラの強み
食品工場は一般の建築物と異なり、衛生管理や温湿度管理、動線計画などに高度な専門性が求められます。食品工場を建設するにあたり、豊富な施工実績があるヤマウラでは、以下のようなサポートが可能です。
- 単なる建物の施工にとどまらず、食品製造に適した安心で使いやすい空間づくりを実現
- 用途地域や建築基準法といった法的制約を踏まえ、敷地条件や事業計画に応じた最適なプランニングを提供
- 建ぺい率や容積率、道路条件、防火規制などを総合的に検討し、将来的な拡張性や操業効率まで見据えた計画を提案
- 食品工場に欠かせないライフライン(上水・下水・電気・ガス)の確保や排水処理施設の整備を、インフラ整備から稼働後のサポートまで一貫して対応
- 稼働後もメンテナンスや改修、運用上の課題解決などをサポート
- 加工食品の海外輸出する場合の食品安全を確保する国際認証のFSSC22000取得のサポート
- 食品工場の施設整備に関わる補助金のアドバイス
上記に加え、ヤマウラでは、設計段階から地域特性に応じた提案も可能です。地域ごとに異なる気候条件や周辺環境、住民との関係性を踏まえた計画を行うことで、操業の安定性と地域社会との共生を両立させます。
こうした総合力により、ヤマウラは食品工場建設において「安心して任せられるパートナー」として、多くの企業から信頼を集めています。
まとめ
食品工場の建設では、「用途地域」と「立地条件」に関する正しい理解が成功のカギです。建築基準法に基づく建ぺい率や容積率、道路条件、防火規制などを踏まえた土地選びが欠かせません。また、周辺環境や住民への配慮も重要であり、信頼できるパートナーと共に計画を進めることで、安心かつ効率的な工場建設が実現できます。
長野県・山梨県の工場建設はヤマウラへ
ヤマウラの食品工場建設専門ブランド「オイシールド」では、衛生を保つゾーニングや防虫・防鼠対策、製造工程の監視システムなど提案しています。山梨・長野で工場を建てたいならぜひ一度ヤマウラへご相談ください。