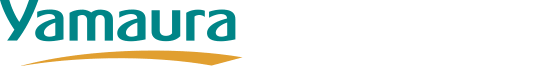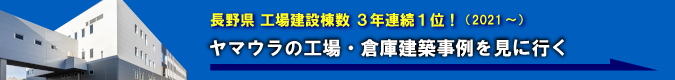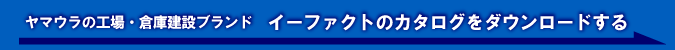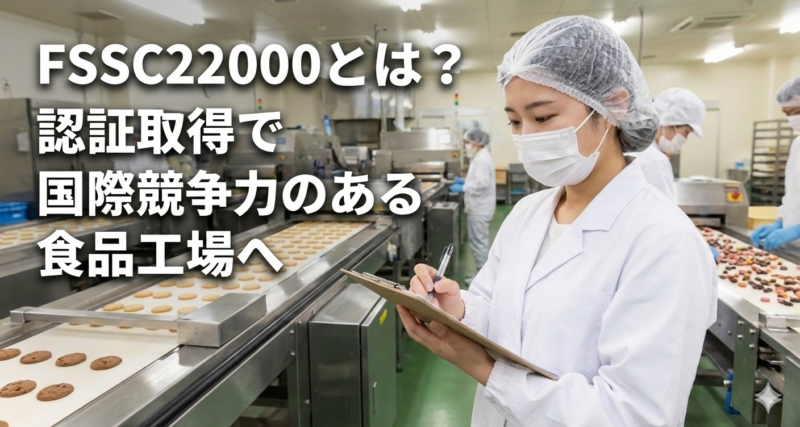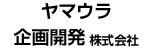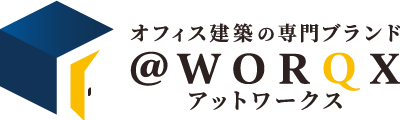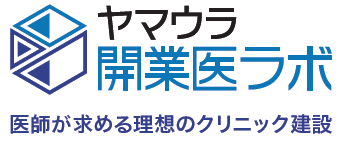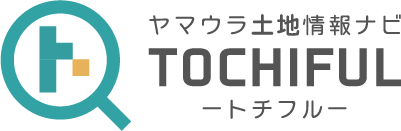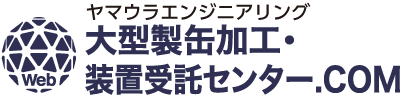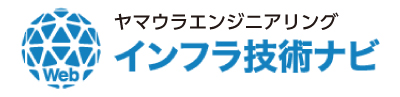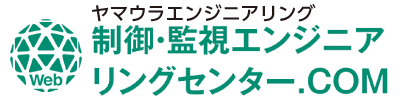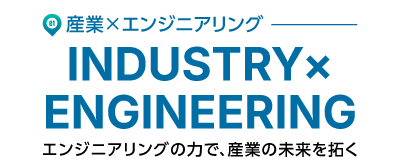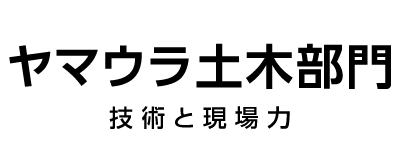建設コラムColumn
近年の食品安全法改正やHACCP義務化、さらには労働力不足による自動化需要の高まりなど、食品工場を取り巻く環境は大きく変化しています。本記事では、食品工場経営者が設計・建築プロジェクトを成功に導くための実践的なポイントを包括的に取り上げました。
目次
食品工場の建築や改築を考えたら
食品工場といえば工場の中でも難易度の高い建設といわれています。計画を進めるうえでまず何から手を付けるかも悩ましいかもしれません。まず、以下のようなところから始めてみてはいかがでしょう。
プロジェクトの目的の確認
食品工場の建築・改築プロジェクトを開始する前に、まず明確にしてほしいのは「なぜ今、工場を建設・改築するのか」という根本的な目的です。
単純な生産能力の拡大なのか、HACCP対応や食品安全基準への適合なのか、労働力不足に対応するための自動化推進なのか、目的によって設計アプローチは大きく異なります。一つではないとして、ある程度優先順位をつけておくことも大切です。
また、お客様とのつながりを広げる「見せる工場」や、ショップでの販売など、ブランディングを兼ねて人を呼ぶことを視野にいれた工場づくりなどの企画もありうるでしょう。これらの要望も計画段階から明確にしておく必要があります。
法令や補助金の最新情報をチェック

食品工場の建設では、関連法令の正確な理解と遵守が重要となります。特に食品衛生法については時代背景に合わせて様々な改正がされます。関連の食品衛生法施行規則等も併せ、建築主の立場からもしっかり最新の情報を確認しておくとよいでしょう。
公的な制度としては、規制だけでなく建設や設備導入を推奨する各種補助金等の施策も用意されています。特にHACCP対応や省エネルギー設備導入、自動化・省力化に対する支援制度は充実しています。申請条件等が厳格に定められているため、実際に使えるかどうかはある程度仕様等が決まってから確認が必要になりますが、初期段階で使えそうなものを念頭に入れておきたいものです。
公的な制度の動向を知ることで、国の指針や国際的な流れを確認することができる点も重要です。世の中に何が望まれているか、大きな方向性を踏まえることは企画を立てるうえでも参考になるでしょう。
設備や業界のトレンドを知る
食品工場の設備技術は急速に進歩しており、最新トレンドを把握することで競争優位性の確保と将来の陳腐化防止が可能になります。現在の主要トレンドとしては、人手不足の流れを受けたロボット化・自動化やAIを利用した在庫管理、検査技術など、様々な動きがあります。
自社が建設しようとする分野の食品工場で、注目の技術などは改めて調べなおしておきましょう。AI技術の進展等で一気に動きが変わってしまう分野も出てくるかもしれません。
大枠の予算や資金調達の方向の決定
建設という大きなプロジェクトの初期段階では、予算を正確に定めることは難しいだけでなく、無駄な作業になってしまう場面もあるかもしれません。しかし、お金の問題はプロジェクトの成否を決める重要な要素。資金調達についてはできるだけ早めに計画・準備する必要があります。
どのぐらいの予算ならば現実的なのか決算等のデータを確認しラインを定めておくことや、融資はどのような金融機関から調達が可能かなどの情報収集はすぐに取り掛かっておきましょう。政府系金融機関の設備資金融資、リース活用、クラウドファンディングなど多様な選択肢の情報も一通り確認し、大まかな方針は早めに定めておくとよいでしょう。
設計事務所選びはこのような点をチェック

建築主として食品工場の設計に携わるとき、最も重要なのはパートナーとなる設計事務所選びでしょう。難易度の高い建築となる食品工場ですから悩ましい選考となりますが、以下のような観点でチェックしておくのがお勧めです。
設計施工分離とデザインビルド
まず、決定しておいた方がよいのは、発注方式をどうするかです。大型の建物の発注方式として、設計施工分離方式とデザインビルド方式(設計施工一括方式)があります。公共工事でよく選ばれる設計施工分離方式では、設計と施工を別々の会社に発注するため、設計の中立性と施工品質のチェック機能が期待できる一方、責任の所在が分散し、コストや工期の管理が複雑になる傾向があります。
デザインビルド方式では、設計から施工まで一つの会社が一括して担当するため、責任の明確化とプロジェクト管理の効率化が図れます。食品工場の場合、HACCP対応や特殊な衛生設備の設計・施工には高度な専門知識が必要であり、豊富な経験を持つ会社によるデザインビルド方式が効果的な場合が多いとされています。
設計から施工まで、信頼できる会社の目途がつくのであれば、一貫して全体を任せてしまう方がスムーズといえるでしょう。
(参考記事:工場建設の設計・施工)
食品工場の経験と実績
食品工場設計は、一般的な工場建築とレベルの違う専門性が要求されます。食品衛生法等の法的な知識や衛生管理、温度・湿度管理、防虫防鼠対策、排水処理など、食品製造特有の課題への対応経験が設計品質に直結します。設計事務所選定においては、工場建築の実績数だけでなく、具体的な施工事例や対応技術を確認することが重要です。
特に重要なのは、自社の製造品目に類似した食品工場の設計経験です。また、設計を依頼する会社の設計士がHACCP設計士等、専門資格を保有しているかなども、会社の体制の確認ができる指標となるでしょう。
コミュニケーションの取りやすさ
食品工場建設プロジェクトは通常1年から数年にわたる長期プロジェクトとなるため、設計士との継続的なコミュニケーションが不可欠です。設計段階での要望の反映、施工中の変更対応、竣工後のメンテナンスまで、様々な局面でスムーズな意思疎通が求められます。
専任担当者の配置や定期的な進捗報告体制など、基本的な体制はもちろん、ITを利用したファイル共有やコミュニケーション体制なども整っているとよいでしょう。もちろん、発注者に対して専門用語を使わずに分かりやすく説明できるといったスタッフの人的な能力もしっかり確認してください。
BIMやシミュレーションソフトの技術活用
設計会社選びには、先端の技術にタッチアップしているかどうかという点も重要な指標となるでしょう。
Building Information Modeling(BIM)により建物の3Dモデルを作成することで、建物が完成する前にイメージを明確にすることができます。設計修正箇所の早期発見、施工性の事前検証、維持管理情報の一元化など、その効果は大きなもの。特に食品工場では、衛生区画の明確化や動線の検証において、BIMの視覚化機能が大きな効果を発揮します。
また、食品工場では生産ラインの設置やゾーニング、温度・湿度・気圧等の設定・管理が複雑になるため、設計段階でのシミュレーションが重要となります。各種シミュレーションソフト等を用いてこのような課題を解決する技術を持っているかは、ぜひ確認してみてください。
食品工場設計時のチェックポイント

食品工場の設計では設計事務所とともに建物の使用者側も一緒に考えていくべきポイントは多いもの。実際の設計工程に入ったとき、どのようなことを中心に検討するか、以下のようなポイントから考え、ぜひ実現したい要望等を準備しておくとよいでしょう。
安全性を守るHACCPに対応した設計
食品関連の事業に携わる方ならよくご存じの通り、現在の食品工場はHACCPの手順を基にした衛生管理が義務化されています。HACCPそれ自体は建物や設備自体の基準を定めたものではありませんが、効果的・効率的な運用には設備の整備も欠かせません。
(参考記事:HACCPに対応するために知っておくべき7原則12手順とは?)
工場の建設は、1ランク上の安全で効率的な生産のフローづくりを実現する機会としたいものです。それを可能にするのが、綿密なゾーニング・動線計画の設定です。
まず、清潔区域と汚染区域を明確に分けることで、異物混入や交差汚染のリスクを低減すること。次に、従業員、原材料・製品の動線、廃棄物の動線といった形でそれぞれの動線を分離し、無駄な接触や混雑を避けた配置を行います。
併せて、空調システムによる陽圧管理による菌や微生物の陽圧管理の設計等、細かく定義を作成し、設計を行っていきます。
安全性の観点では、防虫・防鼠対策や排水システムについても、全体を通して注意深く確認が必要となってきます。
生産性・メンテナンス性の確保
上記のようにHACCPの導入でしっかりと安全性を高めつつ、生産性の確保も忘れてはいけません。食品工場の生産ライン等の検討は考えるべき要素の多い、非常に複雑な課題となります。
そこでぜひ活用したいのが専用のシミュレーションソフト。代表的なのが、Plant Simulation、FlexSim といったソフトで、ロットサイズの変更やラインの連携など、できてしまってからの変更が難しい部分を仮想空間で試すことができます。高額なソフトですので、自社での導入が難しい場合は特に、依頼する設計事務所で使用できるのが望ましいでしょう。
また、建物各所のメンテナンス性にも注意を払っておきたいものです。掃除の手間がかかる、壊れやすいといったことがあると、十二分に検討して高めたはずの生産性も発揮することができません。
生産する食品の特性に合うよう、床・壁・天井の材質や各設備の選定、モニタリング機能やスペースの適度な冗長性などを総合的に盛り込み、無理なく長く使える建物づくりを考えていく必要があります。
食品工場の設計施工はヤマウラにご相談ください
以上のように、食品工場の設計は高い専門性が必要な難易度の高い仕事となります。慎重に行いたいパートナー選びですが、ヤマウラなら、例えばHACCP設計士(中級)30名・HACCPコーディネーター14名・米国FDA公認FDQI取得者2名在籍(2025年7月現在)と、専門的な知識を持ったスタッフにお任せいただける体制を整えています。
設計・施工一貫で、設計はもちろん、土地や補助金のご相談から建築までスムーズにお客様のご要望にお応えします。長野県・山梨県で食品工場の建設をお考えなら、ぜひまず専門ブランド「オイシールド」をもつヤマウラにご相談ください。